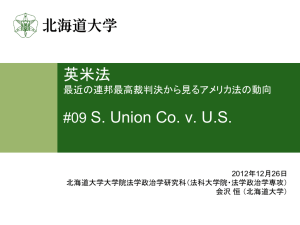Part 1 排出権取引市場 ―進化を続ける欧州取引市場と日本の現状― BNPパリバ銀行 東京支店 市場派生商品本部 カーボン・マーケット部長 富田 宏 2005年から活発化した排出権取引の主要な市場で EUA)を割り当てる。対象企業は、自身の排出が同 ある欧州と日本は、それぞれ独自の仕組みのもと、 排出枠内でとどまった場合、余剰排出枠を売却でき 成長を続けている。欧州は、2013年以降の第3フェ るが、反対に排出量が上回った場合には、目標遵守 ーズの枠組みも合意され、ポスト京都に当たる2013 のため、排出枠を市場から購入することができると 年以降の取引がすでに始まっているなか、さまざま いう制度である。実際の排出が与えられた、もしく な課題も発生し、制度の歪みの修正に関する努力を は購入した排出枠を上回った場合には、その違反企 進めている。それに対して、2008年から2009年にか 業は罰金を支払わなければならない。これが「キャ けて大きな変化をみせた日本の排出権取引市場は、 ップ・アンド・トレード方式」である。 欧州との連動性を高めながら、新しい排出権取引の 制度づくりに向けて動き出している。 対象となる温室効果ガスはCO 2 に限定され、25カ 国の約5000社、1万1500カ所の大量排出事業所が EU-ETSの対象となっている。本制度の第1フェー 1. 進化を続ける欧州排出権取引制度 ズは2005年から2007年、2008年から2012年までの第 2フェーズは、2008年から始まる京都議定書の第1 (1)成長を続けるEU-ETS 約束期間と重なる。 欧州排出権取引制度(European Union Emission 世銀統計によれば、2005年の世界の排出権市場規 Trading Scheme=EU-ETS、以下EU-ETS)は、欧 模は、7.1億CO2トン、額に換算した場合、108億ドル 州連合(European Union=EU)が京都議定書で課 の規模であったが、その後急成長し、2008年には された8%の温室効果ガス排出削減を効率よく達成 48.1億CO2トン、1263億ドルに拡大したが、EU-ETS することを目的として、2005年1月1日より開始さ で扱われるEUAおよびセカンダリーCER(後述) れた世界で初めての国際的な排出権取引制度である。 は、その93%を占めている。 EU-ETSは、企業によるCO 2 排出総量に上限を設 定し、加盟各国が、それぞれの国別割当計画(Natio- (2)動き出している2013年以降の第3フェーズ nal Allocation Plan=NAP、以下NAP)に基づき EU-ETSは、開始から5年がたち、規模の成長だ 排出枠(European Union Allowance=EUA、以下 けではなく、域内企業の活動にさまざまな影響を与 2010.5 3 図表1 排出権市場の成長(米ドルベース、2005〜08年) 過多となった第1フェーズのEUAの価格はほぼゼロ に近いレベルまで落ちたという経験から、次フェー (百万ドル) 150,000 ズへの持ち越し可能性( バンキング )への関心が Other JI P-CDM S-CDM EU-ETS 100,000 高い。電力市場の自由化が進んでいる欧州では、 2013年から始まる第3フェーズ以降の電力販売も始 まっており、2013年以降のEUAの取引はすでに開始 されている。そのようななかで、現在市場でクレジ 50,000 ットの質が注目されているというのは、これが第2 フェーズから第3フェーズへ持ち越しが可能な排出 0 2005 2006 2007 2008(年) 出所:世銀、States and Trends, 2006/2007/2008よりBNPパリバ銀行作成 権かどうかという視点からである。 今までは、EU-ETSで流通できる排出権と京都議 定書のもと発行された排出権との乖離は、一部の大 えるようになったが、ポスト京都の議論が進展して 規模水力のみであった。2013年以降の国際的な枠組 いない2008年12月12日、欧州首脳会議は、2013年以 み、CDM改革の方向性が決まらないなか、欧州は、 降のEU-ETS第3フェーズの概要も含めた気候変動 独自の基準を示している。 パッケージを合意した。 CERは、第3フェーズ後に順次EUAとの交換をす 主な内容としては、EUAの分配は、2013年以降は ることが予想されているが、国際合意がない場合で 2010年を基準年として、毎年前年比1.74%削減、国 も、最貧国、もしくはEUおよびプロジェクト実施国 別の排出枠分配基準は、2013年以降は欧州委員会が 間の合意があった場合に限定するなどの条件を付加 設定することとなる。2013年以降、電力業界は、基 している。セクターでみた場合、再生可能、省エネ、 本的に100%オークション方式による分配、他の産業 燃料転換、交通、廃棄物処理については引き続き利 へは、基本的には無償配当を継続し、オークション 用が可能とみられているが、その他の分野について 比率を徐々に引き上げるものの、すべてオークショ は、今後の欧州委員会における議論を注視する必要 ンとするタイミングは、2027年とされた。 がある。 2008年半ばから顕著となった景気後退の影響を受 けて、排出枠の割当方法などについては、同年1月 (4)航空セクターへの適用 に公表された当初案から後退したとの見方はあるが、 現在の域内企業・事業所をカバーするEU-ETSに いちばん重要な点は、欧州が、ポスト京都の合意の 加え、欧州に乗り入れる航空各社も、2012年から欧 有無にかかわらず、EU-ETSを進めていくという決 州独自の排出権取引制度の対象となる。1990年代の 意を示した点であろう。 航空業界に対する規制緩和の影響により航空輸送は 増加、航空業界からの排出はEU全体の3%を占める (3)注目されるクレジットの質 ようになり、同セクターの排出削減は大きなテーマ 第3フェーズの特徴は、ポスト京都合意の有無に であった。元来、国際航空/海上輸送は、京都議定 かかわらず、域外のプロジェクトからのクレジット 書に記されているように国際的な枠組みで制度づく を活用する道を開いていることであるが、そのなか りが進むはずであった。これまでの国際航空協会は、 で、クレジットの 質 について市場で注目されて 国際線を含まない国内のフライトのみを規制の対象 いる。 とする方向性を打ち出していたが、EUは、その案は 欧州景気動向の落ち込みなどから目の前での需給 満足できるものでないとの考えから、EUに乗り入れ の逼迫は起こっておらず、現状では2012年まで欧州 るすべての航空会社を対象とすることを決定した。 排出権価格は大きな変化はないとの見込みが大勢を 本案では航空業界のみが対象となる排出枠も創設 占める。そのようななか、EU-ETSでは、第1フェ し、今までのEU-ETSの割り当てが国別に行われて ーズのEUAが第2フェーズへ持ち越しできず、供給 いたのに対し、欧州域内統一ルールを適用するよう 4 2010.5 【特集】環境特集 2 になる。EU内外の航空会社は、自社の排出に関する の接続が大きく遅れ、一時は上記移転の可否を疑問 データを報告し、排出枠は、業界のベンチマークを 視する見方も広がるまでに至った。最終的には2008 用いて割り当てられることとなる。なお、排出デー 年10月半ばに両システムは正式に接続し、大きな混 タのモニタリングは、すでに2010年1月1日からス 乱はなかったものの、排出権取引における制度リス タートしており、着々と準備が進んでいる。 クを市場関係者に認識させた出来事であった。 今後、国際的枠組み、もしくは地域的な枠組みが その後、2009年には、付加価値税の課税を免れよ 構築され、国際輸送の分野が異なる制度下の規制が うとした排出権取引がフランスをはじめとした主要 進んだ場合、欧州委員会は、それぞれの制度の「質」 国で摘発、2010年には、CO 2 割当量管理システムを を判断し、規制の対象や方法を修正していきたいと 狙ったサイバー攻撃が散発的に起こり、標的にされ の考えである。このように他の地域の制度との比較 たデンマークの国別登録簿が、1月にシャットダウ の可能性が出てくる本制度は、航空業界という限定 ンする事態も発生している。 的なセクターにおける制度づくりではあるが、排出 そして、2010年、より大きな問題として注目され 権取引制度全体にさまざまな示唆を与えるものと考 たのはリサイクルCERである。リサイクルCERとは、 えられる。 一度EU-ETS制度内で償却されたCERが、償却され EU域外の航空会社も規制の対象に含めることに関 た国の政府によって、EU-ETS域外に売却された しては、その法的な妥当性が問われており、米国系 CERであるが、本来このリサイクルCERは、EU- の航空会社は、欧州委員会を相手に本制度に反対す ETS市場に還流しないことを前提として売却された る行動を起こしている。また、航空業界の中には、 ものの、取引所を含むEU-ETS内に売却されたため、 温室効果ガス排出削減自体には賛成しながらも、欧 排出権取引所のCERのスポット取引は、一時停止さ 州1地域による規制には反対する国連下の国際条約 れる事態を起こした。欧州委員会およびEU-ETS参 を推進するグループも存在している。今後、さまざ 加各国は、同様の事態が再び起こらないように、償 まな排出削減の枠組みの推移を見守りたい。 却済みのCER等を市場に還流しない取り決めを発表、 さらなる市場の混乱を防止する手立てを打つことと (5)制度の不完全性 なった。 EU-ETSがスタートしてから5年がたったが、域 欧州では、このようにさまざまな制度的な問題が 内の経済活動に排出権取引制度が浸透した半面、さ 表面化しているなか、排出権取引制度の改善、改革 まざまな制度の問題も指摘され、現在も、よりよい の努力を続け、排出権取引制度の定着を物語って 制度の構築のための試行錯誤が繰り返されている。 いる。 京都メカニズムのもとで発行された各種クレジッ トの発行や移転等を管理するために、国連は、国際 2. 日本の状況 取引ログ(International Transaction Log=ITL) を設置、EU-ETSは、制度内で独自の取引システム (1)高まる欧州市場との連動性 (Community Independent Transaction Log= 京都議定書の第1約束期間がスタートした最初の CITL)を設置している。京都クレジットをEU-ETS 年である2008年は、景気動向の影響から前年度より に移転・取得するためには、ITLとCITLの接続が必 温室効果ガス排出量の減少、そしてコンプライアン 要となるが、2007年、ITLの運用が開始され、日本、 ス・バイヤー注1による海外からの排出権購入によっ ニュージーランド、スイスなどの国が、次々とITL て、かつて厳しいと思われていた京都議定書のマイ との接続を開始するなか、当初2007年までにITLと ナス6%の目標達成も可能となり、京都議定書を取 接続するはずであったCITLは、システムの問題や政 り巻く日本の目標達成状況は当初思われていた構図 治的な問題から再三遅れていた。他国と同時期の とは少し異なる様相を呈してきている。そのような ITL-CITL接続を前提とし、大量のCERの移転が なか、2008年から2009年は、日本のコンプライアン 2008年12月1日に行われることになっていたが、そ ス・バイヤーの排出権購入行動が大きく変化した時 2010.5 5 期でもあった。 において個々のプロジェクトごとの技術、環境、社 会的な評価を行い、将来プロジェクトから出てくる 注1:EU-ETSでは、同制度の下、排出削減義務を負っている企業のこと を指す。日本では、一般的に経団連自主行動計画参加企業となる。 プライマリーCERを取得することであった。 それに対して、欧州のコンプライアンス・バイヤ ーは、2005年のEU-ETS発足後、EUAの代替として (2)プライマリーCERとセカンダリーCER 利用するためEUAの市場取引価格より安価で獲得で CERは、発行リスクのあるプライマリーCERと発 きるCER獲得をめざした。当時、アジア、ラテンア 行リスクのないセカンダリーCERとに分けられる。 メリカにおいて日本と欧州バイヤーは、激しいクレ プライマリーCERは、CDM事業からの将来のCER ジット獲得競争を繰り広げていたが、欧州バイヤー 買い取りであるため、国連からCERが発行されるま の提示する価格は、EUAの上昇に伴い上昇し、価格 での、建設、操業などのプロジェクト実施リスク、 競争力を高めていった。 事業者の信用リスクおよび国連の登録手続きにかか 2007年より欧州ではセカンダリーCERの取引所取 る登録リスクなどの「デリバリー・リスク」がある。 引が開始されたが、2006年以降、世界各国のCDMプ 取引の方法は、相対取引中心のため、価格には、そ ロジェクトでデリバリー・リスクが顕在化したこと れぞれのリスクを考慮する。 によって、セカンダリーCERの市場価格とプロジェ それに対して、セカンダリーCERは、すでに発行 クトごとに決められるプライマリーCERの価格は、 されたCERであるため、上記デリバリー・リスクは 次第に乖離することになった。毎年の獲得義務を課 ない。セカンダリーCERは、欧州の取引所でも活発 されている欧州のコンプライアンス・バイヤーは、 に取引されていることから、現在では価格透明性が 排出権の獲得時期を確定する必要に迫られており、 高まり、EUAを若干下回る価格で取引されている。 セカンダリーCERを活用する傾向があるのに対し、 理論的には、プライマリーCERは、デリバリー・リ 日本のコンプライアンス・バイヤーは、毎年決まっ スクを伴う分、セカンダリーCER価格を下回る価格 た数量のCERを確保する必要はないため、デリバリ となる。 ー・リスク発生時であっても、減少分もプライマリ 京都議定書発効前後、世界の排出権価格は、世界 ーCERで補う傾向にあった。 銀行のCER買取価格(ドル建て)が指標の役割をし そのような日本の購入傾向の違いのひとつのター ていた。従来、日本の政府およびコンプライアン ニングポイントは、2008年のリーマン・ショック以 ス・バイヤーの基本的な排出権獲得戦略は、途上国 降の急激なEUA/CERの排出権価格の下落および大 図表2 排出権価格関係図 価格 クレジットの種類 市場取引されている排出権 透明性のあるEUACERスプレッド EUA 2010年にERUオークション を開始 セカンダリーCER セカンダリーERU プライマリー CER とセカン ダリー CER との価格差は、 それぞれのリスクにより決定 AAU プライマリーCER プライマリーERU VER 出所:各種資料よりBNPパリバ銀行作成 6 2010.5 AAUの価格は相対取引 で決定 【特集】環境特集 2 幅な円の対ユーロの上昇であった。 るのは、当然のことである。しかし、2つの市場は、 プライマリーCERの最大供給国である中国は、そ CERなどの国際的に取引されている排出権によって、 れらを売却する際の下限価格を設定しており、2008 すでに密接につながっており、今後日本国内の排出 年後半の欧州での排出権価格が下落した後でも、同 権取引制度が整備され、ポスト京都の議論が進んで 下限価格を下げることはなかった。そのため、プラ いくなか、新しい展開を迎えると考えられる。 イマリーCERとセカンダリーCERの価格がほぼ同じ か、逆転する事態となった。2008年、日本のコンプ 注2:AAU取引によって移転された資金を直接的・間接的に温室効果ガ ス削減に寄与する活動に使うこと。 ライアンス・バイヤーは、中国のCER下限価格と同 レベルになったセカンダリーCERの購入が広がるこ とになったが、プライマリーCERからセカンダリー 3. 終わりに:EU-ETSの貴重な経験 CERへのシフトは、デリバリー・リスクと価格の関 係を考えた場合、自然な流れだと考えられる。 日本では、環境税や炭素税や排出権取引制度の導 日本のコンプライアンス・バイヤーの行動のもう 入に関する長い議論はあったが、2009年9月民主党 ひとつの転機は、日本政府によるチェコ共和国、ウ 鳩山政権の成立後に具体的に動き出した。地球温暖 クライナからのAAU購入であった。 化対策の第一の柱は、中期目標では、2020年までに 経団連自主行動計画では、自身の削減努力に加え 1990年比25%排出量を減らすことや、キャップ&ト て、排出権の購入を行うことによって、政府の京都 レードでの排出権取引制度の導入をうたっており、 議定書目標達成に寄与するものであり、政府が扱え 1年後の成案をめざしているもののその実現には多 る排出権は同様に購入の対象となることから、企業 くの課題を抱えている。それは、日本がすでに高い もAAU取引を行えるのがEU-ETSとの大きな違いで エネルギー効率を達成している点だけでなく、EU- ある。 ETS成立までの長い道のりの例のように同制度を整 日本政府および企業が購入するAAUは、移転・売 備するためには、エネルギー政策、電力市場をはじ 却から得られる資金がGHG排出削減または環境改善 めとする産業政策、金融政策などのさまざまな分野 に活用することとされている仕組みであるグリーン との地道な協議が求められる点にある。 投資スキーム(Green Investment Scheme:GIS) 今後、オーストラリア、ニュージーランド、米国 を活用したものであるため、今後それらの資金の適 でも排出権取引市場は形成されていき、アジアでも 注2 日本、そして韓国が独自の制度をスタートさせるこ 切な活用、レポーティングなどを行うグリーニング の手法には引き続き課題は残っているものの、AAU とになろう。各国とも、それぞれのエネルギー政策、 の簡便なデリバリー、大量の供給余力、そしてプラ 環境・社会政策、そして産業構造を踏まえた制度づ イマリー/セカンダリーCER/ERUよりも安価で購 くりを進めており、国際的には、さまざまな特徴を 入可能なAAUの購入も自然な流れと考えられる。 もった各国独自の制度が濫立する様相を呈してきて 排出権取引は、2005年以降、さまざまな変化を繰 いる。 り返しながら発展しているなか、2009年に入り、日 排出権取引が、枠のやり取りを行うだけで、排出 本のコンプライアンス・バイヤーは、プライマリー 削減には役に立たないとの議論があるが、排出権取 CERの購入から離れ、一時期はセカンダリーCERの 引は、温室効果ガス排出削減を最低限のコストで達 購入を進めたものの、現在の購入の中心は、AAUに 成する方法をみつける手段であり、 「資金還流」を補 完全にシフトしたと考えられる。 完する役割を果たす。EU-ETSでみられたような、 EU-ETSと日本の仕組みは、全く異なるものであ 新しい市場の形成には幅広い議論が重要である。大 り、そのなかにいる企業は、属する国・地域の制度 きな制度を構築するためには、時間をかけつつも、 によって購入傾向が大きく異なる。したがって、日 幅広い意見を集約し、長期的なビジョンを示してい 本のコンプライアンス・バイヤーが、欧州のコンプ くことが肝要である。EU-ETSの経験は他国の排出 ライアンス・バイヤーと大きな購入傾向の違いがあ 権市場の構築に役立っていくこととなろう。 2010.5 7